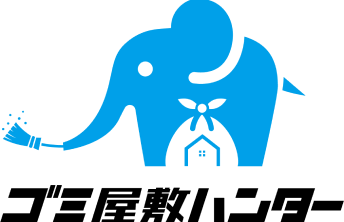「部屋が散らかり過ぎてどこから片付ければ良いか分からない…」
そんな悩みを抱えている人は意外と多いです。
掃除や片付けを後回しにした結果、汚部屋になってしまったという人もいるのではないでしょうか。
そこで、ここでは汚部屋を効率的に掃除する手順や部屋を綺麗に保つコツまで丁寧に解説していきます。
片付けのモチベーションが上げるための方法も紹介するので、汚部屋の片付けでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
目次
汚部屋を放置するリスクとは
汚部屋で生活していると、その状態に慣れてしまい「片付けなくても良いか…」と思ってしまうことがあるでしょう。
しかし、汚部屋を放置すると深刻な問題へと発展してしまう可能性があります。
そこで、ここでは汚部屋を放置することで生じる可能性がある6つのリスクを解説していきます。
- 害虫や害獣が発生する
- 健康に悪影響を及ぼす
- 精神的ストレスや孤独感の増加
- 火災や事故の危険性
- 近隣トラブルにつながる
- 最悪の場合は立ち退きや強制撤去も…
害虫や害獣が発生する
ゴミや食べ残し、飲み残しを放置していると、ゴキブリ、コバエ、ネズミなどの害虫・害獣が発生する可能性があります。
特に、蒸し暑い夏は害虫の繁殖スピードが早いため、一気に増えてしまうことが多いです。
害虫や害獣は不快なだけでなく、食中毒やアレルギーの原因にもなるため放置しないようにしましょう。
健康に悪影響を及ぼす
汚部屋にはホコリ・カビ・ダニが溜まりやすく、アレルギーや喘息などの呼吸器疾患、アトピーや肌荒れなどの肌トラブルなどを引き起こす可能性があります。
さらに換気が不十分だと、空気中の菌がこもり、免疫力が下がってしまう方も多いです。
特に免疫力が低下している高齢者や乳幼児がいるご家庭では注意しましょう。
精神的ストレスや孤独感の増加
汚部屋での生活は気が付かないうちに精神的なストレスを増加させることがあります。
また、散らかった空間では集中力が低下し、仕事や家事が進まないことも多いです。
さらに、汚い部屋を誰にも見られたくないという思いから、人付き合いを避けるようになり、孤独感が深まってしまうという人も少なくありません。
火災や事故の危険性
部屋にゴミや物が散乱していると、ヒーターの熱やコンロの熱による引火や電気系統のトラブルから火災が発生するリスクが高まります。
特に、コンセントや電気コード周辺にホコリが溜まることによって起こる「トラッキング火災」に注意が必要です。
また、床に物が散乱していると転倒やつまずきによる事故やケガのリスクも高まります。
近隣トラブルにつながる
汚部屋に溜まったゴミや汚れから発生する悪臭や害虫は、壁や天井を超えて周囲の住宅にまで影響を及ぼすことがあります。
その結果、近隣住民から苦情が寄せられ、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
特に、アパートやマンションなどの共同住宅では問題になりやすく、管理会社やオーナーを通して注意を受けることもあります。
【参考】「ごみ屋敷」対策に関する調査
最悪の場合は立ち退きや強制撤去も…
管理会社やオーナーからの何度も警告があったにも関わらず汚部屋を放置していると、契約違反となり、立ち退きや契約解除を求められる可能性があります。
さらに、行政指導が入るケースや地域の条例に基づく強制撤去となったケースも少なくありません。
オーナーや行政から警告を受けた場合は、速やかに片付けを行いましょう。
汚部屋掃除を始める前にやるべき準備

汚部屋の片付けを効率よく進めるためには事前の準備が大切です。
ここでは、汚部屋掃除を始める前にやっておくべき準備を解説していきます。
- 現状を把握し、目標を明確にする
- 必要な掃除道具をそろえる
- 地域のゴミの分別ルールを把握する
- 作業範囲とスケジュールを決める
現状を把握し、目標を明確にする
まずは今の部屋の状態を冷静に判断しましょう。
ゴミの量・部屋の広さや数などを確認して、自分一人で作業が可能かどうか判断することが大切です。
一人で掃除ができそうにない場合は、家族や友人に手伝ってもらう、片付け業者に依頼する、などの方法を検討しましょう。
必要な掃除道具をそろえる
掃除をスムーズに進めるために、あらかじめ必要な掃除アイテムを揃えておきましょう。
そろえておきたいアイテムは以下の通りです。
- ゴミ袋(地域指定のもの)
- ビニール袋
- はさみ
- 掃除機
- 雑巾・ウェットシート
- 軍手
- マスク
これらのアイテムをまとめて持ちやすいボックスなどに入れておくと、作業がスムーズに進められます。
地域のゴミの分別ルールを把握する
各自治体によってゴミの分別方法や収集日が異なるので、事前に地域のルールを確認して正しく仕分けができるようにしておきましょう。
特に、汚部屋の片付けの際には大型ごみを処分する可能性もあるので、大型ごみの処分方法を調べておくと安心です。
地域のルールを守らないとゴミが回収されず、近隣トラブルの原因にもなるため、しっかりと調べておくことが大切です。
作業範囲とスケジュールを決める
掃除をする範囲をあらかじめ決めておくことで、むだな動きや迷いを防ぐことができます。
例えば、今日は玄関から、明日はキッチン、など部屋やスペースごとに区切って作業日を分けるのもおすすめです。
時間や体力に合わせて無理のないスケジュールで行いましょう。
効率が良い汚部屋掃除の順番

汚部屋掃除を成功させるためには、正しい順番で効率的に進めることが大切です。
やみくもに始めると途中で疲れてしまったり、逆に散らかってしまったりすることも少なくありません。
ここでは、効率的に汚部屋掃除を進めるための流れを具体的に解説していきます。
- 玄関・通路を確保する
- 明らかなゴミを分別・袋詰めする
- 必要な物と不要な物を分ける
- 物や種類ごとに整理整頓する
- 清掃作業をする
- 不用品を処分する
1.玄関・通路を確保する
まずは家の出入りや移動がしやすくなるように、玄関から部屋までの通路を片付けて動線を確保しましょう。
動線が確保されることでゴミや荷物が運び出しやすくなり、作業効率が大きくUPします。
最低でも人ひとりが無理なく通れるスペースを確保しましょう。
2.明らかなゴミを分別・袋詰めする
明らかにゴミと分かるもの(空き缶・レジ袋・プラスチック容器・使った後のティッシュなど)をどんどんゴミ袋に入れていきましょう。
捨てるか迷うようなゴミではなく、明らかなゴミをゴミ袋に入れていくだけでも、部屋はかなりスッキリとしてきます。
この段階では、捨てるか迷うようなゴミは一旦残しておきましょう。
3.必要な物と不要な物を分ける
ゴミがある程度減ってきたら、残った物を「必要な物」と「不要な物」に分けましょう。
ポイントは1年以上使っていない物は処分候補として考えることです。
衣類・雑貨・紙類などカテゴリごとに作業を進めていくとスムーズに進みます。
どうしても迷ってしまう物は、仮置き場として箱などを用意し、その中に入れておきましょう。
4.物や種類ごとに整理整頓する
残すと決めたものは、使用頻度や用途に応じて収納場所を決めましょう。
例えば、よく使う物は手の届く場所に、年に数回しか使用しない季節物やストック品などは棚の奥に収納するのがおすすめです。
中が見える収納ケースやラベルを活用すると、片付け後に探す手間を減らすことができます。
使ったら元に戻す仕組みを作るためにも、この作業は非常に大切です。
5.清掃作業をする
物の定位置が決まって整理整頓ができたら、ようやく清掃作業にとりかかります。
まずは棚・壁・床のほこりを掃除機で吸い取り、雑巾やウェットシートで拭き掃除をしましょう。
カビが生えていたり、臭いが気になったりするところには専用の洗剤や消臭スプレーを使うと効果的です。
水回りや窓ふきなども行うと、一気に部屋が綺麗になります。
6.不用品を処分する
片付け作業で出た粗大ごみは地域の粗大ごみ回収に申し込むか、不用品買い取り業者に依頼して処分しましょう。
まだ使える家電や家具は、リサイクルショップやフリマアプリを利用して手放すのもおすすめです。
また、地域の回収で出せる燃えるゴミは、一気に出すと迷惑がかかってしまうことがあるので、複数回に分けて出すようにするのがおすすめです。
汚部屋掃除のモチベーションを上げる方法

掃除をしなければいけないと分かってはいてもなかなか体が動かない…という方は少なくありません。
そこで、ここでは汚部屋掃除のやる気を引き出し、最後まで取り組めるようにするためにコツを5つ紹介します。
- 小さな目標を決める
- 掃除後のご褒美を準備する
- 無理のないスケジュールを組む
- 好きな音楽やラジオで気分を上げる
- 家族や友人に手伝ってもらうのもおすすめ
小さな目標を決める
いきなり全部片付けようとすると、何から手を付ければ良いか分からなくなって手が止まってしまうことがあります。
まずは、この引き出しだけ、今日は玄関だけ、といったような小さな目標を立てて、それをクリアしていきましょう。
小さな達成を積み重ねることで片付けや掃除への自信がつき、次の作業への意欲が湧いてきます。
掃除後のご褒美を準備する
この部分の掃除が終わったらお気に入りのお菓子を食べる、ゆっくりとお風呂に入る、映画を見る、など自分へのご褒美を用意しておくのもおすすめです。
面倒で嫌な作業でもご褒美があることで行動に移しやすくなり、掃除のモチベーションを維持できます。
部屋が全て片付いたらずっと欲しかったソファーを買う、などの大きな目標を立てるのも効果的です。
無理のないスケジュールを組む
ゴミの量や汚れによっても異なりますが、汚部屋掃除には数日~数週間程度かかることが多いです。
1日で終わらせるというような無理なスケジュール設定にすると、体力や気力が持たず、途中で中断してしまう可能性があるので注意しましょう。
少しずつでも継続して掃除を続けていく方が、最終的に綺麗な部屋を目指すことができます。
好きな音楽やラジオで気分を上げる
掃除中には自分の好きな音楽やテンションが上がる曲をかけるのもおすすめです。
音楽には気分を高揚させたり、集中力を高めたりする効果が期待できます。
ラジオが好きな人はポッドキャストなどを使ってみましょう。
面倒な作業のモチベーションを上げるためには、自分が快適に作業できるような工夫をすることも大切です。
家族や友人に手伝ってもらうのもおすすめ
一人で作業をすると途中で嫌になったり、孤独を感じたりしてしまうことがあります。
信頼できる家族や友人に手伝ってもらうことで、会話をしながら掃除ができ、作業効率もUPさせることができます。
第三者の視点が入ることで、不用品の判断もしやすくなるので、人の手を借りるのもおすすめです。
部屋を綺麗に保つためのコツ

一度綺麗になった部屋も、何もしなければすぐに元の汚部屋に戻ってしまいます。
大切なのは綺麗な状態の部屋を維持するということです。
ここでは、部屋を清潔で快適な状態に保つためのコツを5つ紹介します。
- 物を増やさない仕組みをつくる
- 物の定位置を決める
- 使ったら元の場所に戻す習慣をつける
- ゴミをすぐに捨てる習慣をつける
- 定期的な掃除・片付けの時間を設ける
物を増やさない仕組みをつくる
整理整頓されて片付いた状態の部屋を維持するためには、まず物を増やさないということが大切です。
新しい物を買う時には一旦本当に必要か考える、衝動買いをしない、など自分なりのルールを決めましょう。
物の量をコントロールすることで、散らかりにくい仕組みをつくることができます。
物の定位置を決める
家にある物の定位置を決めることで「出しっぱなし」を防ぐことができます。
筆記用具はこの引き出し、リモコンはテレビ台の上のかご、のように物の定位置を決めることが大切です。
ラベルを付けることで家族がいても、迷わずに元に戻すことができます。
使ったら元の位置に戻す習慣をつける
片付いた状態を維持するためには、日々の小さな行動をすることが大切です。
何かを使ったら必ず元に戻すというだけでも、積み重ねると大きな差になります。
最初は意識しないと難しいかもしれませんが、続けていくうちに習慣化して部屋が散らかりづらくなります。
ゴミをすぐに捨てる習慣をつける
ゴミを机の上や床などに放置せずに、すぐにゴミ箱に捨てる習慣をつけましょう。
小さなゴミ箱を手の届く範囲に置いておくと習慣化しやすいです。
そして、ゴミ回収の時に小さなゴミ箱のゴミをまとめて捨てに行くと家にゴミが溜まるのを防ぐことができます。
ゴミ捨てを習慣化することが汚部屋脱却の第一歩です。
定期的な掃除・片付けの時間を設ける
週に1回、月に1回など、ご自身のライフスタイルに合わせて片付ける日を設けましょう。
平日は仕事で忙しいという人は土曜日の午前中に片付けるのをルールにしてしまうなど、短時間でも片付けを日常生活の中に組み込んでしまうのがおすすめです。
また、毎日10分だけでも片付けるのを続けると部屋が散らかりにくくなります。
片付け業者に依頼するのもおすすめ

自力で汚部屋の片付けをするのが難しいと感じたら、片付け業者に依頼するのもおすすめです。
プロに任せることで大量のゴミや不用品を短時間で効率的に処分でき、自分で片付けなければいけないという精神的な不安も軽減できます。
また、ゴミの分別や思いの荷物の運搬、清掃まで一括で対応してくれる業者も多いので、仕事や育児で忙しい人にもおすすめです。
信頼できる片付け業者の選び方
片付け業者に依頼することで汚部屋の片付けや清掃は一気に進みます。
ただし、依頼する業者を間違えると、トラブルに発展する可能性もあるので注意が必要です。
ここでは、信頼できる片付け業者を選ぶポイントを紹介します。
- 複数の業者で相見積もりを取る
- 実績や口コミの内容をチェックする
- 説明や対応の丁寧さをチェックする
- 不用品が多い場合は買取もしている業者がおすすめ
複数の業者で相見積もりを取る
信頼できる片付け業者に出会うためには、最低でも3社以上から見積もりを取りましょう。
複数社の見積もりを比較することで費用の相場を把握し、サービス内容からご自身の目的に合う業者を選ぶことができます。
費用が異様に高く、サービスの質が悪い悪徳業者に騙されないためにも、複数の業者で見積もりを比較することが大切です。
実績や口コミの内容をチェックする
業者の公式サイトに掲載されている実績数や過去の片付け事例などを確認して、その業者の実績を確認しましょう。
実績数が多い業者ほど片付けや清掃作業に慣れているため、作業がスムーズに進むことが多いです。
また、実際に業者を利用した方の口コミを口コミサイトやSNSで確認すると大変参考になります。
説明や対応の丁寧さをチェックする
初回の問い合わせの時や見積もりの時の対応で、説明の丁寧さやコミュニケーションが図れるかを確認しましょう。
こちらの疑問に対して丁寧に答えてくれる業者は作業中もコミュニケーションが取りやすいことが多いです。
分からないことがある場合は、遠慮せずすぐに質問しましょう。
不用品が多い場合は買取もしている業者がおすすめ
家具や家電、雑貨などまだ使える不用品の数が多い場合は、買取も同時に行ってくれる業者を利用するのがおすすめです。
買取金額を作業金額から差し引いてくれる業者もあるので、費用を節約することもできます。
買取を行っているかについては、公式サイトや問い合わせ時に確認しましょう。
まとめ
汚部屋を片付けるのは精神的にも身体的にも大きな負担となることがあります。
掃除を始める前に簡単な準備を済ませてから、効率よく片付けをスタートさせましょう。
一人で片付けるのが難しい場合は、家族や友人に協力してもらう、片付け業者に依頼するなどの方法を選ぶのもおすすめです。
思い切って部屋をリセットすることで、心地よい快適な暮らしを取り戻しましょう。